 |
|
|
|
|
|
|
|
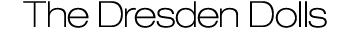  ← Prev | 1 | 2 | 3 | Next → |
普通のドラマーは一定のリズムをキープするのが役目ですが、あなたのスタイルはそうではなく、非常に特別なものであると思います。ああいったドラミングは、いつ頃から自覚して目指すようになったんですか?
Brian:実はかなり早い段階で、ああいうプレイ・スタイルに出遭っていたんだ。11歳くらいの時に、父親が偉大なジャズ・ミュージシャンたちの音楽を聴かせてくれるようになって、あと、ジョン・コルトレーンと長年一緒にプレイしたエルヴィン・ジョーンズのドキュメンタリー・ヴィデオを買ってくれたりもしてね。そのヴィデオでのエルヴィンのプレイを観るたびに、ものすごくエキサイトした僕は、父のベッドルームのドラムセットに直行して、彼みたいなドラムを叩こうとしたんだよ。しかも、ただ真似するだけじゃなくて、頭の中でリズムを感じた時に、彼のプレイを模範にしながらそれを進化させようとしたんだ。つまりほんの子どもの頃から、ドラムでイメージを「描き出す」指向性を持っていたってわけ。もちろん、ロック・ミュージックっていう強固な基盤があったのは、すごく僕のプラスになったと思う。ドラマーのいちばん大事な仕事のひとつは、テンポをキープして、他のプレイヤーたちにしっかりした土台を与えてやることだからね。でもそれに加えて、ドラマーっていうのは単にリズムを保つだけじゃなくて、音楽とメロディを奏でることもできるし、すごくユニークな「声」も体現できるんだっていう哲学を手に入れたおかげで、もともとのロック的なドラム・スタイルにユニークな要素がブレンドされたと思う。1960年代の多くのプレイヤーが、ジャズから影響を受けたのとすごく似てるよ。ジンジャー・ベイカーとかミッチ・ミッチェルとか、ブラック・サバスのビル・ウォードとか、あの時代の偉大なドラマーの多くがそうだっただろ。ロック・ミュージックにずっと欠けてたのが、その瞬間瞬間にクリエイトする能力だと思うんだ。僕は、ドラムにはもっともっと可能性があると思ってて、そいつを引き出そうと常に努力してるんだよ。
アマチュア時代に、仲間とバンドをやるにあたって「そんな変なことしなくていいから、普通にビートを刻んでろよ」というようなことを言われたりしたこともあったんじゃないですか?
Brian:ああ(笑)、そういうこともあったね。親友に言われたことはなかったな。僕がやろうとしてることや僕の考え方を、ちゃんとわかってくれてたからね。でも、たまに年上の連中とプレイしたときなんかに、「へえ、妙なことをやるな。スタンダードじゃないね」と言われることはあった。でも、どんなアートフォームでも、最も大きく前進した人っていうのは、標準とはまったく違う考え方を取り入れて、線の外側を塗ることからスタートした人ばかりだってことに、僕は前から気づいてた。だから、変なプレイをしてどんなに批判されても、やり込められたような気はしなかったね。だからといってフリー・ジャズをやってたわけでもないんだよ。そこまでブッ飛んだことはやってなかったし。でも、18歳でジャズを本格的に聴くようになったことが、ドレスデン・ドールズの中で取り入れようとしたことの原点になったのは事実だ。それまでの僕はひたすらロックのドラミングを手本にしてプレイしてるだけだったけど、曲作りに対してスタイリスティックなアプローチをするアマンダと出遭ったことで「彼女とならロック以外のいろんな要素を取り入れることができる」って閃いたんだよね。それで、過去にやってたギター・バンドでは一度も許されなかったやり方で、音楽にドラムで「色をつけよう」と試みるようになったんだ。
つまり、まさにアマンダと出遭ってドレスデン・ドールズとなった瞬間、あなたの理想のドラム・プレイ環境を得ることができたわけですね。
Brian:うん、まさにその通り。彼女と出遭ったことで、それまで僕が学んできたこと全てが意味のあるものになったし、ロック・バンド時代には全然足りてなかった部分で成長することができたんだ。ロック・バンドじゃ本当に限界があって、「ビートをキープして、同じ強弱で叩き続けろ」って言われるだけだったけど、アマンダとやるようになって、ドラム・プレイへのまったく別のアプローチが可能になったんだよね。単にベースのリズムに応えるとかじゃなく、もっと彼女の詞の「歌い方」に応える形でプレイできるようになった、とでもいうのかな。多くのドラマーは、そういうプレイはしないと思う。ほとんどが、揺るがないようなリズムどりに固着しようとするからさ。つまり僕の場合、歌の伴奏をやってるピアニストのようなアプローチをとるようになったんだ。曲にしっかりした基盤を与えるドラミングというよりも、曲のストーリーに色をつけるようなドラミングをするわけ。あと、いろんな違ったタイプの音楽を聴くようにもなったし、もっとジャズを聴きたいと思うようにもなったよ。そんなふうにして、キャリア上でも最も影響を受けてきたのが、ジャズ・ミュージックの雄弁なプレイ、空間の使い方だったんだ。
それでは、そんなドレスデン・ドールズとしての表現スタイルを確立していったプロセスについて、あらためて振り返ってみてもらえますか?
Brian:まずひとつに、僕たちは「ユニット」として一緒にプレイするやり方を学んできたと思う。それぞれ自分のパートだけ上手くいけばいいっていうんじゃなくてね。それ以前の僕たちにはできなかったような組み合わせが可能になったというか、ひとつの音楽ユニットとして表現ができるようになった。その点は今でも進化し続けてると思うんだけど、ただ時々フラストレーションを感じることもあるよ。というのも、僕はもっともっと音楽的に進化したいと心から思ってるのに、アマンダはその点に関してはそれほど強く感じていないんだ。彼女はもっとソングライティングに関心があるみたいでね。そういうわけで、僕らはそんなふうにして支え合ってるんだけど、そう、時には喧嘩もするよ。「もっと楽曲を作り込みたいんだ!」っていう僕に対して、アマンダは「とにかく曲を書く時間をちょうだい!」って感じでさ。ただ、僕らみたいなバンドには、その両方が必要なんだよね。それにドレスデン・ドールズの音楽スタイルは、実際のところアマンダが作る曲によって決定づけられてる。バンドのサウンド概念を「こういうサウンドでなきゃダメで、そのためにはこういう方向性で作業しなきゃダメだ」と決めつけるようなやり方じゃなく、アマンダが「んーっ……よし! できたわよ! 今持ち合わせてるのはこれだけだから、それをできるだけ形にしていきましょ」みたいな感じでやっていくわけ。だから……そう、バンドが一緒にプレイしていく中で、ソングライティングが成熟して精製されていくことを願うのみ、とでもいうか。結論としては「音楽的な進化・成長が、ソングライティングをさらによいものにしてくれたら」と思ってるよ。
ドレスデン・ドールズの作曲について、もう少し詳しく訊きたいんですが、基本的にはアマンダが書いた曲にあなたがドラムをつける、というパターンですよね?
Brian:そう、基本的にそれが、リハーサル・スタジオで初めて合わせた時から使ってる雛型だね。僕はドラムキットに座って、彼女がピアノの前に座って、僕が「さあ、何でもいいから弾いていってよ。どんどん合わせるから」と声をかけたんだ。今までずっと、その哲学でやってきたわけ。僕は実際かなりラッキーだと思う。どっちが書いた曲をアルバムに入れるとかで、彼女と争ったりしたことは1度もないからさ。2人とも、お互いの長所を活かすようにして、本物の「チーム」としてより良い音楽を作る努力をしてるんだ。主導権を巡って闘ったりするんじゃなく、彼女は僕の叩きたいようにドラムを叩かせてくれるし、僕も彼女に書きたいように歌詞を書いてもらってる。絶対に「こんなのダメ!」なんて言わないよ。アマンダが書く歌詞のテーマや、彼女がすごくパーソナルな歌詞を書くことに対して、不愉快に感じることなはいかって訊かたりもするけど、気になったことは1度もないし、万が一なったとしても、僕はそれを声に出して言う立場にはないと思うんだ。人種差別主義の児童虐待者の話とか(笑)道徳的に煮ても焼いても食えないような、どうしようもないゴミみたいな歌詞でも書かない限りはね。むしろ個人的な心情に関しては、表現できるものならどんなに不安定な心情でもどんどん表現しなよ、って彼女に勧めたのは僕なんだ。そうすることで、リスナー側の自由な気持ちを高めることができるんじゃないかと思ったのさ。普通みんな恐がって書かないような歌詞を書いてみせる彼女の大胆さを見て、みんなも自分自身の中に勇気を見出してくれるんじゃないか、ってね。
なるほど。本当に素晴らしいチームだと改めて実感します。ギターが入る場合のアレンジはどうやって進めるんですか?
Brian:スタジオで作業する時は、曲にプラスになりそうな質感のサウンドを、いろいろ集めるようにしてるんだ。たとえば、ファースト・アルバムではギターやベースやストリングスも使ったわけだけど、それは、ドラムとピアノだけじゃ曲に何かが欠けていると思ったからだった。でも一方『Yes, Virginia』では、もの足りないからじゃなく純粋にサウンドを補強するために、そういう楽器を加えたわけ。だから今の方が、もっと自信を持ってギターをプレイしている気がするよ。つまり、ギターを取り入れる必要があるからじゃなく、取り入れたいからプレイしてる、っていう感じなんだ。ギターって本当にきれいな音をしているし、もともと弦楽器をピアノに合わせた時の音がすごく好きなんだよね。だから、依存するんじゃなくてセンスよく利用する、っていうのがポイントなんじゃないかな。
わかりました。では最後に、ミュージシャンとしての長期的な目標を教えてください。
Brian:基本的に、その時その時に感じていることを可能な限り雄弁に表現できるようになる、ってことだね。その助けをしてくれるのがドラムだから、もっとドラムの腕を磨かなきゃならないと思ってるよ。言葉で自分の考えをもっと表現できるようになるためには語彙力を磨くのと同じで、それを音楽を通してやりたいんだ。言葉だけじゃ届かない、もっと奥深い場所に向かって語りかけるためにね。音楽の持つ力を語る時、僕自身が経験した中でも特にパワフルだと感じるのは、音楽を通していろんな感情の起伏を表現できるってことと、自分の周りの世界と自分自身の感情を音楽を通して加工することができる、ってことなんだ。僕にとって、自分の本質っていうのを最も根本的な形で解釈したものが、自分のドラミングなんだよね。僕の身体の外にあって、しかも僕自身と結びついているもの――僕にとって精神的な癒しを与えてくれるものなんだ。僕は特定の宗教を信仰してはいないけど、言ってみれば音楽こそがそういう存在で、自分に自信を与えてくれて、自分がこの世で生きている価値があるものだと思わせてくれるものなんだよね。だから自分のドラムの腕を、先人の偉大な達人たちに近づけるまで(照笑)磨くことができたら、自分がこの世に生まれたことも無駄じゃあなかった、って思えるんじゃないかな。
がんばってください。では、この後のツアーの成功と、またいつかライヴが観られることを願っています。
Brian:サンキュー!
|
← Prev | 1 | 2 | 3 | Next → Special Issue | Interviews | Articles | Disc Reviews Core BBS | Easy Blog | Links © 2003 HARDLISTENING. all rights reserved. |